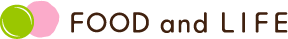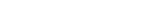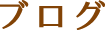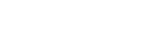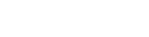あけびのこと
2023-10-14
アケビ・・・
季節の食材の紹介です。
山やスーパーでも美しい紫色が目に留まります。
実はあまり馴染みがないのですが、、、
中学生の頃のアケミ先生のお名前の由来がアケビだったと伺い、
その時初めてアケビを知りました。だからと言って頻繁に使ったことがないのです。
(その色の通りとても美しい先生です!)
アケビは苦味が強く変色も早く、
色々な働きも強いのではと勝手に想像していました。
先日、調理しましたので、
薬膳から簡単にまとめます。
アケビ科のアケビ
【薬膳編】
微苦・平
肝胃膀胱
気の巡りをよくする、胃腸の調子を整える
腎の働きを良くする
水の流れをよくする、尿の出をよくする
など
*小林先生は幼い頃、登山中に、アケビの中身を食べていたとのこと。。。
*アケビを味噌炒めにして頂きました!(写真がないのですが)
少し苦味が効いていましたが、夜に上記のような働きをしっかりと感じましたよ!
アケビの茎は木通という名の生薬としても使われています。
龍胆瀉肝湯などにも使われています。
働きが異なりますので下記に紹介です。
木通
心・肺・小腸・膀胱
清熱利湿通淋
1.膀胱湿熱の熱性の排尿痛・頻尿・排尿困難・残尿感などに
2.瀉心火
心火上炎の口内炎・舌炎・煩躁・ほてり・喉の渇き・不眠・濃縮尿などに
熱湿痹証の関節の痛み・関節運動障害などに
3.産後の乳汁分泌不全・乳房脹満感などに使用される。
4.通経
瘀血で生理が来ない状態・月経不順などに使用される。
四肢の冷感・凍傷などに使用される。
*毒性があり多量の服用で中毒を起こす可能性がある。そのため少量を使用する。
妊娠者はNG
参照
農林水産省 HP
中薬大辞典
薬膳を学ぶ人のための身近な漢方講座テキスト
(農林水産省 うちの郷土料理から引用です)
↓↓↓
* 歴史・由来・関連行事
あけびは、山形県民にとって欠かすことのできない郷土の味覚として根づいており、春には新芽、秋は果実を食用に。つるはつる細工などに活用される。
山形県であけびの栽培が盛んになったのは、1970年代から1980年代あたりから。天童市で採取されたあけびが関東で好評を博し、本格的な栽培がはじまった。村山地域や置賜地域が主産地になっており、県全体の生産量は全国トップレベルを誇る。薄紫色、ピンク色など種類や系統によって見た目も若干異なり、食卓に彩りをそえる役割もある。
全国的には種のまわりの白い部分を食べるのが一般的だが、山形県では皮の部分を食べるという全国的にも珍しい食文化がある。味わいはほろ苦く「あけびの味噌詰め焼き」のほか、煮物、和え物、天ぷら、ぬた和えなど、さまざまな料理に調理して食される。
* 食習の機会や時季
あけびの季節は8月中旬から10月中旬。内陸部の家庭では旬の食材として、シーズンの間に一度か二度はあけび料理が食卓にあがるという。地元の人にとってあけびはわざわざスーパーマーケットで買う食材というよりも、裏山に自生しているものをとってきたり、庭先で育てていたり、ご近所からおすそ分けしてもらったりするものという感覚。あけびの皮は天日に干して保存しておき、煮物などにも利用される。
あけびは捨てるところのない万能果物といわれていて、ひと昔前は、種子から油をとっていた時代もあった。
* 飲食方法
調理前に、あけびの種を取りのぞき、フキンで水気を拭き取っておく。ひき肉や舞茸を味噌や砂糖で煎り煮して、それをあけびの皮に詰めたらタコ糸などで結んで、ていねいに焼いてから食べる。
あけびの皮はほろ苦い風味があるが、味噌と合わせることで食べやすくなる。皮の部分はナスのように味がよく染みて、炒めものや煮物にすると噛み締めた時に味が染み出して美味である。
* 保存・継承の取組(伝承者の概要、保存会、SNSの活用、商品化等現代的な取組等について)
高い生産量からもわかるとおり、あけびは山形県民にとって馴染み深い食材。里山では近隣から採集する人も少なくない。「あけびの味噌詰め焼き」のほか、さまざまなあけび料理が伝承されている。

【薬膳理論の小話】
2022-11-15
0D0B2EE4-A673-4CD8-9D73-A9FD48D56F56
10/20(木)は秋の土用入りです
2022-10-17
秋も深まり、気温は過ごしやすくなりましたね。
頭痛、気持ち悪い、食欲低下、冷え、耳、鼻、疲れ、心配など色々と不調が出る声を聞きます。
天気の変動が激しいので、心身ケアが難しいのは当たり前と思っても良いかもしれません。
夏に疲れを溜めた方、更年期の方、ストレスを溜めてしまった方など
その方がどんな状態なのかによりおすすめの食事も変わりますが、
薬膳体質がわかる方は、一度自分の心身を見つめて
体質に合わせた食事を心がけ優しいご飯を食べましょう。
ストレッチや散歩などもおすすめです。
そうではない方はまずは
お腹に優しい食事をゆっくりと食べましょう。
おかゆや蒸し料理と温めたものを心がけてくださいね。
間もなく秋の土用です。
秋にも土用があり、旧暦の暦の季節の変わり目にあたります。
この期間私たちはお粥を取り入れたりお腹を特に大切にしていきます。
お粥は調理法の薬膳としては素晴らしいのでぜひ取り入れてみてください。

※※※
薬膳料理教室FOOD and LIFE
自由が丘 中目黒 オンライン
※※※
夏ですね・・・夏といえば・・・?!
2018-06-05
おはようございます!
今朝もカーテンを開けたら強い日差し…
梅雨入りは??と思うほど夏を感じます。
さて夏といえば・・・とうもろこし

薬膳では元気をつけてくれて、体の余分な水分を出してくれるので、疲れやすい、疲れがとれにくい、
むくんでいる時にオススメです。
利尿作用があるとうもろこしのひげも捨てずに取り入れたいですね。
今週6月8日(金)10:30~12:00
夏の過ごし方を学ぶ夏を元気に過ごすレシピ作り~の開催があります。
薬膳で考える夏の過ごし方や、夏にとりたいオススメの食材などをお話いたします。
1時間半で3800円の、薬膳を気軽にお楽しみいただける講座です。
薬膳初めての方も大歓迎ですので、お気軽にお越しくださいませ!
こちらの、薬膳を気軽にお楽しみいただける講座は、
他にも薬膳グラノーラ作り、血行をよくするレシピ作りなどいろんなテーマで開催いたします!
詳しくは、こちらをご覧くださいm(_ _)m
東京自由が丘
薬膳料理教室FOOD and LIFE
~薬膳でカラダもココロも元気に!~
https://foodandlife.co.jp/
「いちご」はどんな働きがあるの??
2018-03-13
こんにちは。
今日は食材シリーズのブログです!
最近はクリスマスの前から初夏くらいまで出回るいちご。
今の時期もスーパーでよく見かけますよね。
大好きな方は多いと思います。
おいしいからと何気なく食べているいちごですが、ちゃんと薬膳的効果があるんですよ。

春は、寒さで体の中にとじこもっていた陽気が上昇しはじめる時期。
気温の変化に応じて、上手に陽気が昇ればよいのですが、急激な変化に体が追いつかず、
人によっては頭痛や目の充血、ほてりなどがあらわれることがあります。
いちごは、体をやや冷やす作用があり、体にこもった余分な熱を冷ますちからがあるので、
春にはもってこいのくだものなのです。
ほかにもいちごには胃腸の働きをととのえ、体の水分を補う効果があるのですよ!
おいしいだけでなく・・・優秀な食材ですよね。
年末は高級品のいちごですが、春が近くなり、旬を迎えるころには、お手頃価格で出回ります。
旬の食べ物には、ちゃんとその時期にあった効能をもっています。自然ってすごいですね。
FOOD and LIFEでもイチゴを使ったメニューがございます!
4月5日(木)10:30~ 応用コース/花粉症の薬膳
花粉症の予防や改善の考え方をお伝えする内容です!
花粉症は、花粉の時期だけでなくそれまでの時期をどう過ごすかが大切なのですよ!!
花粉症でお悩みの方もそうでない方もぜひお越しください。
ご予約はHPもしくはメールにて承ります!
東京自由が丘
薬膳料理教室FOOD and LIFE
~薬膳でカラダもココロも元気に!~
https://foodandlife.co.jp/
きんかんの働きとは・・・??
2018-03-05
1月頃から3月頃まで、期間限定で店先に並ぶきんかん。
小さくて地味な存在からか、食べたことがない方は多いと思います。

柑橘類は、皮にも栄養が豊富に詰まっているといわれ、ビタミンCのほか、血行を促進する成分などが豊富に含まれています。
きんかんは、柑橘類のなかで唯一皮ごと食べられる数少ないくだもの。
食べないなんてもったいないですね!!
薬膳的には、きんかんにはさわやかな香りで気をめぐらし、気分をすっきりさせ、消化を促進させる効果があるといわれています。
そして、乾燥する咳を抑えてくれるという、ほかの柑橘類にない効能を持っています。
寒い季節、のどかカサカサして咳が止まらない…といった症状があらわれやすくなります。
そんなときは・・・きんかんの出番です。
はちみつにも肺やのどを潤す効果があるので、きんかんと組み合わせて使うと、相乗効果で咳を止めてくれるの力が
強くなるのです。
きんかんのはちみつ漬けをストックしておき、のどの調子が悪い時は、エキスを水で割って飲む…なんて使い方をしてみてもよいですね。
3月9日には、きんかんを使ったスイーツを作るイベントがございます!
3月9日(金)10:30~12:00
レッスン代3,800円(税込)
ご入会金不要でご受講いただけます!
ご予約はこちら
簡単に作れるきんかんスイーツで、春もげんきに過ごしませんか?!
わずかですが残席もございますので、ぜひお越しくださいませ!!
東京自由が丘
薬膳料理教室FOOD and LIFE
~薬膳でカラダもココロも元気に!~
https://foodandlife.co.jp/
「白きくらげ」は何に良い??
2018-02-07
皆さま、こんにちは。
前回は「白ゴマ」でしたが今回は「白きくらげ」についてのお話です。
女性ならば誰しも、しっとりした肌は憧れますよね。
薬膳では肺と皮膚はつながっていると考えられています。
つまり、「肺を潤せば皮膚も潤う」ということにつながり、
肺を潤す力が強い食材に、必ず白きくらげがあげられます。

白きくらげはきのこの仲間で、食物繊維やビタミンDが含まれ、肺を潤す作用のほかに、
のどの渇きを抑えたり、乾燥性の咳を落ち着かせる作用もあります。
白きくらげも黒きくらげと同様、柔らかくしたほうが体への吸収がよくなるため、
コトコト数時間煮て、ドロドロになるくらいがおすすめです。
圧力鍋があれば柔らかくする時間が短縮できます。
そこへはちみつや氷砂糖を入れれば、立派な薬膳デザートに。
「お肌が潤うなら!」と飛びがちな食材ですが・・・
むくみやすい体質の方や、
水分代謝が悪い体質の方は、
注意が必要です。
その潤う力の強さゆえ、さらにむくみを助長したり、水分をため込んでしまうことになりかねません。
(かくいう私は、食べた翌日体が重くて大変でした)
そんな時は、辛味と一緒に食べることをお勧めします。
白きくらげのデザートにシナモンを足したり生姜を足せば、辛味によって潤いを巡らせる作用がプラスされるので、
体の負担が軽減されます。
しかし、どんな体質でも、欲張って食べすぎには注意しましょう!
食材の働きシリーズ・・・次回もお楽しみに!!
東京自由が丘
薬膳料理教室FOOD and LIFE
~薬膳でカラダもココロも元気に!~
お肌を潤す●●って??
2018-02-04
皆さま、こんにちは。
今日は立春らしく、気持ち暖かい感じがしますね。
でもまだまだ寒い日は続くようですので、まだ気は抜けませんね!
さて、前回は「黒ごま」についてをブログで書かせていただきましたが、今日は「白ごま」です。

白ごまの色は白。白は肺の働きを高める色とされています。(黒ごまは腎でしたね!)
白ごまは「肺」を潤す力があるとされています。
中医学では肺は皮膚とつながっているとされているので、皮膚の乾燥を改善する力があります。
肺が潤っていると、きめ細かいお肌に!!
そして肺とつながっている臓器といえば大腸。
肺の潤いを高める白ごまは、通じている大腸も潤してくれるので、便通をよくしてくれます。
黒ごまと同様、丸ごと食べるより、すったほうが体への吸収はよいので、なるべくすりごまにして食べるのがオススメです。
目的に応じて黒ごま、白ごまを使い分けるもよし、
両方混ぜて使うのもよし(バランスがよくなるのでおすすめです!)
毎日の食事に、こまめに取り入れてみてくださいね。
ちなみに、FOOD and LIFEのスタッフルームには、「毎日ゴマ生活」ということで、白ゴマと黒ゴマを混ぜてタッパーに入れたものが
ストックしてあります♪
東京自由が丘
薬膳料理教室FOOD and LIFE
~薬膳でカラダもココロも元気に!~
「黒ごま」の働きって??
2018-01-26
こんにちは。
今日はき~んとくる寒さですね。
さて今日は「黒ごま」についてのお話です!
日本人にとって、種子類の中では「ごま」は馴染みのある食材だと思います。
ごま和え、ごま油、ごまドレッシングetc.etc…すっかり定番化していますよね。
ごまはごまでも、薬膳では白ごまと黒ごまでは、効能が少し違うと考えられています。

黒ごまの色はもちろん黒。黒色は腎の働きを高める色といわれています。
薬膳では腎は生命力やアンチエイジングにはとても大切な臓器。
黒ごまは血を補い、生命力を高め、老化をゆるやかにする力があるとされ、
白髪の改善にもよいともいわれています。
お教室でも髪質や白髪が改善した方も!
女性は、35歳をすぎると、生命力は下り坂に入ります。
急激に老け込まないようにするためには、そのころから少しでも、コツコツと腎臓を補う黒ごまのような食材を取ることをおすすめします。
ごまは丸ごと食べるより、すった方が吸収がよくなるので、すりごまを豆乳に入れて飲んだり、和え物に振りかけたりするとよいでしょう。
お教室でも黒ごまを使ったメニューがございます!
◯2月20日(火)19:00~◯
美髪を目指す薬膳~つややかな髪を~(はじめの一歩料理コース) ご予約はこちら
美髪のためのしいたけ•なつめ•ささみの薬膳炒め、エビとブロッコリーのゴマだれサラダ、黒ゴマとあんこの蒸し春巻き、雑穀ごはん、薬膳茶
◯3月8日(木)10:30~◯
アンチエイジングの薬膳~体の中から若くなりましょう~(はじめの一歩料理コース) ご予約はこちら
魚介のうまみたっぷり野菜の蒸し料理、ブロッコリーのナッツ和え、クルミときのこのスープ、バゲットの黒ごまペースト添え、薬膳茶
両日ともに空きがございます!
ぜひお越しくださいませ。薬膳はじめての方も大歓迎です!!
東京自由が丘
薬膳料理教室FOOD and LIFE
~薬膳でカラダもココロも元気に!~
https://foodandlife.co.jp/
寒い季節に必要な食材は・・・??
2018-01-22
東京は今日は雪。
寒さが体にしみてきます。
そんな今日は、元気に冬を乗り越えられる、薬膳的に優秀な食材をご紹介します!

くるみの形は脳に似ていると思いませんか?
その形からか、中国では「脳の働きに良い」といわれています。
・・・そういわれたら、思わず毎日食べてしまいそうですね。
薬膳の効能としては、腎を補うとされ、老化防止や頻尿、下半身の冷えによいとされています。
肺を温める作用もあり、肺の働きも高めてくれます。
さらには豊富に含まれる脂肪で大腸も潤し、便通を良くしてくれる、とても優秀な食材です。
でも、脂肪が多い分、酸化も早いので、なるべく早いうちに使い切るようにしましょう。
我が家では保存は冷蔵庫または冷凍庫で、使う時は必要な分だけ炒ったり、ゆでてています。
特に冬は腎が冷えて弱ると言われる季節。
大寒を過ぎ、この1週間は特に寒くなりそうですね。
クルミをコツコツ食べて、元気に冬を乗り越えましょう。
東京自由が丘
薬膳料理教室FOOD and LIFE
~薬膳でカラダもココロも元気に!~
https://foodandlife.co.jp/
薬膳的!「黒きくらげ」の働きとは・・・??
2018-01-18
皆さまこんにちは。
FOOD and LIFEは、身近な食材を使った薬膳をお伝えしているお教室です。
薬膳の考え方では、食材1つ1つに働きがあると考えていて、それを組み合わせると立派な薬膳料理になるのです。
ブログでも、身近な食材にはどんな働きがあるかをお伝えしていこうと思います!!
まず今日は・・・「黒きくらげ」について。

薬膳では、冬は腎を大切にする季節だといわれています。
腎を補う食材には黒豆、黒ごま、黒きくらげ…と、黒い色の食べ物に多くみられます。
薬膳を勉強して、特に意識してとるようになったものに、黒きくらげがあります。
黒きくらげはきのこの仲間で、ビタミンB群のほかに鉄や食物繊維、カルシウム、マグネシウムなどのミネラルも含まれていて、
存在感のない見た目とは違い(笑)、栄養の宝庫なのです。
薬膳的には、血を浄化して、血の滞りを改善し、血と腎臓を補う力があるとされています。
女性は毎月の生理で血を大量に失うので、常に血の補充を心がけなければなりません。
そこで黒きくらげの出番。味に癖がないので炒め物に入れたり、スープに入れたりと、応用自在に使えます。
黒きくらげは柔らかくすると、吸収が良くなると言われているので、我が家では少し手間ですが、
多めに戻した黒きくらげを、圧力鍋で柔らかく煮てから別の料理にちょこちょこ使っています。
時々生の黒きくらげが出回っているときがありますが、生のものには皮膚にかゆみや痛みを起こすことがあるため、
必ず加熱をして使うようにしましょう。
お教室でも、黒きくらげを使ったメニューがありますよ!
はじめの一歩料理コースでは・・・
・2月22日(木)10:30~ 陰陽バランスから整えるキレイなお肌の作り方の薬膳
・2月28日(水)10:30~ 肩こり改善の薬膳
基礎コースでは・・・
血行改善の薬膳
・3月10日(土)15:30~17:30
・3月29日(木)10:30~12:30
・・・などなどお教室でも黒きくらげは大活躍です!!
こちらのご予約もお待ちしております♪
東京自由が丘
薬膳料理教室FOOD and LIFE
~薬膳でカラダもココロも元気に!~
https://foodandlife.co.jp/
12/22は冬至★
2017-12-23
こんにちは!
FOODandLIFEの小林です。
昨日は冬至でしたね。
冬至に「ん」のつくものを食べると、「運がつく」と言われているので、
それにあやかり私は「だいこん」と「キンカン」のサラダ、「うどん」を食べました笑
来年も良い一年になりますように!

「キンカン」は気のめぐりを良くしてくれます。
忙しいと気が滞りやすくイライラしたり肩こりなどが出てきますので、
今の時期…お仕事に家事に忙しい師走にオススメの食材です。
3月のお教室のスケジュールを更新しましたので、ぜひご予定をチェックしてみてくださいね!
それでは、皆さま、良いクリスマスをお迎えください!
東京自由が丘
薬膳料理教室FOOD and LIFE
~薬膳でカラダもココロも元気に!~
https://foodandlife.co.jp/
小林 優子
お教室では定番の・・・?!
2017-10-10
3連休も終わり、今日からお仕事始動!という方も多いのではないでしょうか。
さて、お教室でも元気の源的な食材として定番な、なつめ。
こちらは、兵庫県丹波篠山産のフレッシュのなつめです!

お教室では、乾燥したものを使うことが多いですが、
フレッシュのなつめは、甘酸っぱくリンゴのような食感です。
なつめは薬膳的に、気や血を補ってくれるので、
疲労回復に良いとされています。
仕事の後や、疲れているとき、元気が出ないとき、に食べたい食材です!
また、中国では「1日3個食べると老いない!」とも言われていますので、
毎日食べたいものでもありますね!
そのまま食べたり、なつめ茶にしたり、スープに入れたり…と、いろいろな楽しみ方ができるのも魅力です!
12月までお教室のスケジュールが出ております。
10月11月も空きのあるクラスもありますので、こちらをご覧ください
東京自由が丘
薬膳料理教室FOOD and LIFE
~薬膳でカラダもココロも元気に!~
https://foodandlife.co.jp/
FOODandLIFE小林優子
夏にうれしい「きゅうり」のこと
2017-07-18
こんにちは!
お天気に恵まれて、海に、山に、川に・・・お出かけ日和の3連休でしたが
とっても暑かったですね。
東京では35度の猛暑日も!
そんな時に食べたい野菜・・・
「きゅうり」

私の実家から届いた写真↑↑
趣味でやっている畑で採れたそうです。
きゅうりは、喉の渇きをとってくれたり、汗をかいた時の水分を補給してくれたり、体の熱を冷ましてくれたり…
と夏の優秀な野菜です!
これから続く暑い毎日、夜ご飯の一品にぜひ食べたいですね!
FOODandLIFE
小林優子
北山のゆるゆる養生法・・♪
2016-12-15
こんばんは。
FOODandLIFEの北山です。
12月中旬。
思わず年末に向けてラストスパート?!、
バタバタと過ごしてしまいますが、皆様はお元気ですか。
FOODandLIFEも少しバタバタとしていますが、
今年の冬は、からだを労りながら過ごしてみています!
色々な養生がありますが、、、今は、
「食べ過ぎない~」養生。。。
食べることが好きなので、
もちろん「いつも、、、」という訳には全くいきませんが笑
食べ過ぎたときには翌日に気を付けたり、トータルで食べ過ぎを気を付けています。
そのおかげで、
食べ過ぎサインがよくわかるようになり、
サインがわかると気を付けるようになります。
そのおかげで、体も心も軽くなりました!
「楽しむ食事」と「体を元気にする食事」を体が分けられているような気がします。。。
今は、私自身も忘年会など嬉しく楽しいお食事会の機会を頂き、おもいっきり楽しみますが、
冬の過ごし方は、
来年のからだに影響をするので、未来のからだのために出来る限り頑張っていますよ~♪
皆様もからだと食事の調節FOODandLIFEと一緒にしませんか。
いつでもお待ちしております!
北山彩子